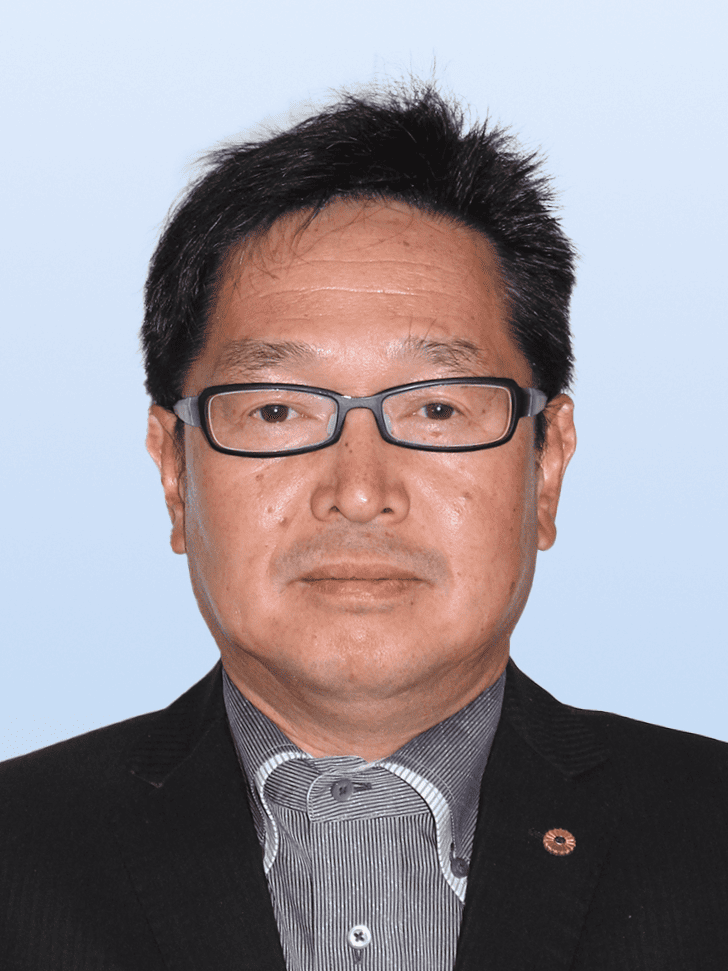現在の社会において、ハラスメントの種類は50以上にのぼると言われています。数年前には30程度だったため、ここ数年で20種類ほどの新たなハラスメントが増加したことになります。
そもそもハラスメントとは、「嫌がらせ」や「いじめ」を指す言葉であり、身体的・精神的な攻撃によって他者に不利益やダメージを与えたり、不快にさせたりする行為です。近年、ハラスメントが増加している背景には、主に以下の2つの要因があると考えています。
1つ目は仕事環境の変化です。多様な働き方や価値観が生まれ、顕在化しています。
2つ目はコミュニケーションの変化です。SNSなどのコミュニケーションツールの進化により、対面でのコミュニケーションが減少し、お互いの思考や感情に向き合う機会が少なくなり、自分とは異なる価値観を持つ人への許容度が狭くなってしまったように感じます。
続いて、企業内でのハラスメントを見ていきたいと思います。代表的なハラスメントとして、「パワーハラスメント(パワハラ)」「セクシャルハラスメント(セクハラ)」「マタニティーハラスメント(マタハラ)」が挙げられますが、最近特に注目されているのが「カスタマーハラスメント(カスハラ)」です。これに関しては、法制化の動きもあります。
企業内で最も相談件数が多いのがパワハラであり、社内でのパワハラが原因でうつ病等の精神疾患を抱え、休職するケースが増えています。会社は、社員に対して安全配慮義務を負っており、労働契約法第5条には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう必要な配慮をするものとする」と規定されています。この配慮には、精神面での健康(心の健康)も含まれます。
ここからはパワハラに絞って、具体的な対応策を考えていきます。パワハラとは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為によって、労働者の就業環境が害されることを指します。令和4年4月からは、中小企業も含め「パワーハラスメント防止措置」を講ずることが義務付けられました。
職場におけるパワハラ防止のために、事業主が講じるべき措置には以下の4項目があります。
1.事業主の方針等の明確化と周知啓発
パワハラを行ってはならないという会社の方針を明文化し、社内に掲示するなどして周知啓発します。さらに、パワハラの6つの類型(身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)を具体的に明示して周知します。
2.相談体制の整備
事前に相談窓口を設け周知します。窓口は総務課、上司、社外の専門家(顧問社労士など)などが考えられます。相談窓口は複数でも良く、相談者が相談しやすい環境を整える必要があります。担当者は、相談者と行為者双方の意見のほか、必要とあれば同僚、上司、部下からも聞き取りを行います。
3.事後の適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認します。事実の確認後は、相談者に対し配慮のための措置とともに行為者に対する措置を講じます。行為者に対する措置の例としては、注意・指導、人事異動、就業規則に基づく懲戒処分などです。さらに、再発防止に向けた措置を講じます。
4.その他併せて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシーを保護し、外部に漏れることを防止します。また、ハラスメントを相談したことを理由に不利益な扱いをしないことを全社員に周知します。プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止は、全社員に通知しておく必要があります。
以上が事業主の講ずべき措置ですが、さらに、ハラスメント防止(セクハラ・マタハラを含む)について就業規則に明示し周知することや、可能であればハラスメント防止の誓約書を取得することも対策の一つです。定期的なハラスメント研修も必要であり、対象を管理職や全社員に分けて実施するなど、企業の規模や状況に応じて工夫が求められます。
上司が部下へ指導する際のパワハラについても考慮する必要があるでしょう。業務上必要な指示や注意、指導は上司の重要な任務ですが、一般的にパワハラは上司が部下に対して行われるものという印象が強く、指導の際の厳しい口調が、部下からパワハラと受け取られる場合もあります。したがって、上司は部下の人格権を尊重しつつ、自信を持って指導することが重要です。
次にパワハラの認定基準についてです。セクハラと似ていますが、認定されるハードルに微妙に違いがあります。パワハラは、人によって指導と感じるかパワハラと感じるかの違いがあるため、客観的基準によって業務上必要で適正な業務指示かが判断されます。一方で、セクハラは被害者がセクハラと感じれば、それが認定されやすい傾向があります。
近年は、同僚間のパワハラ、陰湿ないじめや仲間外れ、自分が主導権を握るための手段としてパワハラ行為を行う、適応障害で休職後に、パワハラが原因で適応障害を発症し休職したと主張するなど、様々な事例がありますが、どの事例においても事実確認の徹底が求められます。
企業がパワハラに適切に対応しなかった場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求や刑事罰を受ける可能性があります。行為者も同様の責任を問われる場合があるため、研修等を通じた周知が重要です。
業務目標に向けて全員が一丸となって、コミュニケーションの取れた職場を目指していきましょう。
参考:厚生労働省 パワーハラスメント対策マニュアル第4版
令和7年2月寄稿